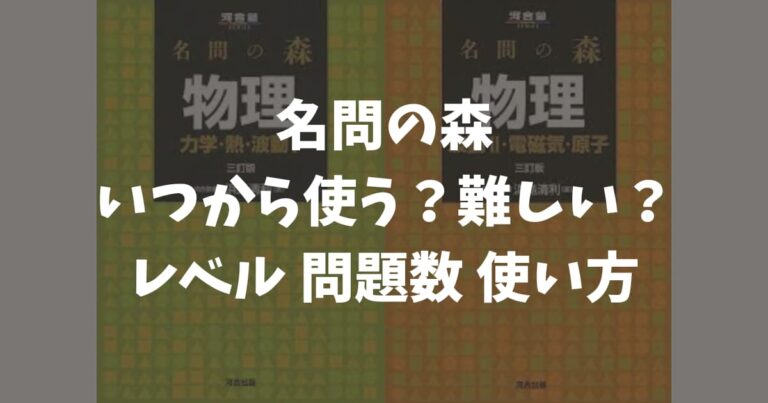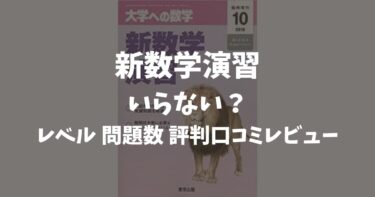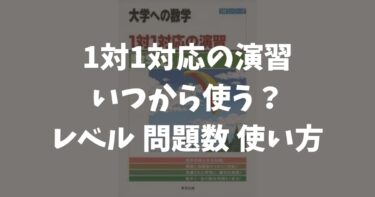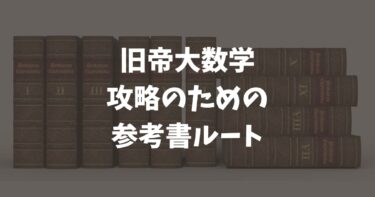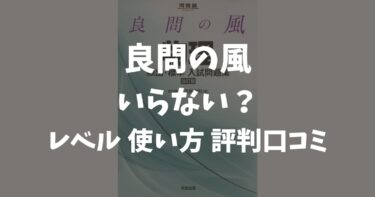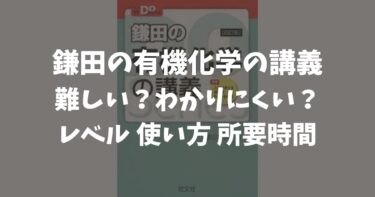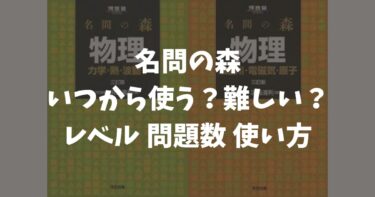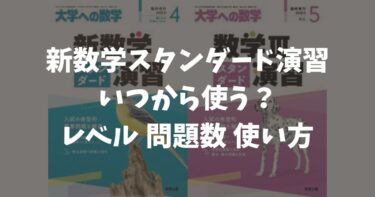今回は「名問の森」(×名門の森)のすべてを解説します!
- 名問の森ってどんな問題集?
- 名問の森のレベルは?
- 評判や口コミはどう?
- 名問の森の使い方は?
この記事を読めば、名問の森についてばっちり分かります!

名問の森のレベル
名問の森は河合塾から出ている物理の参考書です。以下の2部構成になっています。
- 力学・熱・波動Ⅰ
- 波動Ⅱ・電磁気・原子
名問の森のレベルは、「国公立2次標準~最難関」です。
かなり難しい問題がたくさん載っています。
偏差値で言えば、60以上。標準問題までは終えていて、高度な入試問題を使って物理の力をさらに鍛えたい方が使うような問題集ですね。
各問題の難易度は、星の数と色で分けられています。
★★:基本レベル
★:標準レベル
★:応用レベル
★★:難レベル
ちなみに、★★は本当に難しいです。
名問の森の問題数
「力学・熱・波動Ⅰ」編
| 分野 | 問題数 |
| 力学 | 43問 |
| 熱 | 16問 |
| 波動Ⅰ | 14問 |
波動Ⅰでは主に、波の性質やドップラー効果、レンズなどを扱っています。
「波動Ⅱ・電磁気・原子」編
| 分野 | 問題数 |
| 波動Ⅱ | 9問 |
| 電磁気 | 44問 |
| 原子 | 14問 |
波動Ⅱでは主に、波・光の干渉を扱っています。
名問の森の良い評判口コミ
名問の森の良い評判を調査してまとめました!
良問が多く実践的
問題の質の高さに言及する口コミはかなり多かったです。
名問の森には、過去50年間ほどの入試問題から厳選し、さらに手を加えた高品質な問題が掲載されています。
そのため、1問1問の演習から得られる学習効果が高くなっているのがポイントです。
解説が丁寧
名問の森は解説を特に重視している問題集です。
どの問題の解説を見ても、図解を用いつつ、途中の過程を省ぶことなく詳しく説明されています。
また、別解が多数載っているため、1つの問題をさまざまな角度から捉えられるのもポイントです。
微積を使わないのがありがたい
名問の森には微積を使った解答解説が登場しません。
そのため、高度な解法を使うことなく、高校物理の範囲内でばっちり学習できるのが魅力です。
名問の森の悪い評判口コミ
名問の森の悪い評判・口コミについてもまとめました!
しかし、悪い評判はあまり見つかりませんでした。
いくつか見られたのは「厳密性」に関する口コミです。
名問の森では、高校範囲の内容を使って解答解説が作られています。
そのため、厳密性に欠けているのがデメリットです。
とはいえ、入試において厳密性はそこまで重要なことではありません。
厳密性を考えるのは、大学に入ってからで大丈夫だと思います。
名問の森とほかの問題集を比較
名問の森をほかの問題集と比較しました。
物理重要問題集
最新の入試傾向を反映するために毎年改訂されている問題集です。
重要問題集と比較すると、名問の森の方がレベルは少しだけ高いです。
また、解説は名問の森の方が分かりやすいです。
重要問題集と名問の森をどちらも使う必要はありません。
良問の風との比較
標準的なレベルの問題集です。
公式では、名問の森の前に良問の風を使うことが推奨されています。
①物理のエッセンス
②良問の風
③名問の森
この参考書ルートに従えば、順調に物理の成績を上げられます。
ただ、旧帝大など難関大を受験する方は、良問の風を使わずにいきなり名問の森に入るのもアリです。
難問題の系統とその解き方物理(難系物理)
受験物理の最難関の問題集です。
名問の森よりかなり難しく、古い問題もたくさん載っています。
難系は医学部や最難関大学を受験するうえで物理を得点源にしたい方が使う問題集です。
ほとんどの人にとってはオーバーワークになるので、名問の森の後に使う必要はありません。
むしろ、使わない方が良いでしょう。
名問の森が終わったら素直に過去問演習に移るのがおすすめです。
名問の森はいつから使うべき?
名問の森は、標準問題の演習が終わった後に使い始めるべき問題集です。
時期で言えば、高3の夏~秋に使い始めるのがおすすめです。
過去問演習に入る前に、物理を総仕上げするために使いましょう。
名問の森の効果的な使い方
ここからは名問の森の学習効果を上げる使い方を紹介します。
まずは問題文だけを見て考えてみる
まずは入試を想定して、問題文だけを確認して解いてみることからはじめましょう。
ここで意識してほしいのは、じっくり考えることです。
分からないからといって、すぐに諦めるのはやめてください。
じっくり考える過程で物理に必要な思考力や発想力を鍛えられるからです。
思考力や発想力が鍛えられれば、問題をさまざまな視点で捉えられるようになります。
これらの力がなければ、応用レベル以上の問題は解けるようになりません。
特に難関大入試になると、ほとんどの受験生は基本~標準レベルの問題はほぼ確実に取ってきます。
そのため、重要になってくるのは「応用~発展レベルの問題を解けるかどうか」です。
ほかの受験生と差をつけるためにも、じっくり考えて発想力を鍛えましょう。
どうしても分からなかったらヒントを見る
「もう絶対分からない!」と感じるまで問題と向き合ったら、「Point&Hint」というコラムを見ましょう。
「Point&Hint」では、問題を解き進めるのに必要な視点や考え方が紹介されています。
これを見ながら、再度問題の解き方を考えてみてください。
自分の言葉で説明できるようになるまで解答解説を読み込む
自分なりの解答が出来上がったら、解答解説を見て修正します。
解答解説には、入試物理で重要な考え方や解法が詰まっています。
自分の言葉で説明できるようになるまで、しっかり読み込んでください。
特に、解答解説で紹介されている別解に注目しましょう。
紹介された別解を少しずつ使えるようになっていけば、どんな問題にも対応できる確かな力が身につきます。
名問の森はこんな人におすすめ
名問の森はこんな人におすすめの問題集です。
- 物理を得点源にしたい人
- 難関大を狙っている人
まず、物理を得点源にしたい人に名問の森はおすすめです。
名問の森が完璧にできれば、ほとんどの大学では高得点を取れます。
また、旧帝大など難関大を狙っている人にも、名問の森はおすすめ。
難関大の問題を改題したものもたくさん載っているので、実践的な演習経験を積めます。
名問の森正直レビュー!
ここからは、受験生時代に名問の森を愛用していた私による正直レビューです。
力学分野が特に最高
力学分野の問題・解説が最高です。
私は他の物理の問題集もいくつか使いましたが、それらと比べて、力学分野は一番でした。
厳選された問題が載っているので、演習の効率がとても良いです。
解説も丁寧なのもポイントです。
電磁気分野は難しい
この問題集は、電磁気分野がほかの分野と比べて難しいです。
基礎力がない人はまず解けないでしょう。
物理を得意にしたいなら個別指導を利用しよう
- 物理が苦手
- 物理の成績を短期間で伸ばしたい
- 物理を得点源にしたい
という人は、個別指導のトウコベを利用するのがおすすめです。![]()
トウコベ![]() がおすすめな理由は6つあります。
がおすすめな理由は6つあります。
- 東大生がマンツーマンでわかるまで教えてくれる
- 24時間いつでも質問できる
- オンラインで受けられるから便利
- 授業日以外の家庭学習まで管理してくれる
- 一人ひとりに合わせた勉強計画を作成してくれる
- 授業料は受けた分だけだから料金がリーズナブル
トウコベ![]() が気になる人は、無料相談をしてみてください!
が気になる人は、無料相談をしてみてください!
\ 無料で相談できます! /
トウコベで相談してみる!![]()
名問の森のまとめ
名問の森のすべてを解説しました。