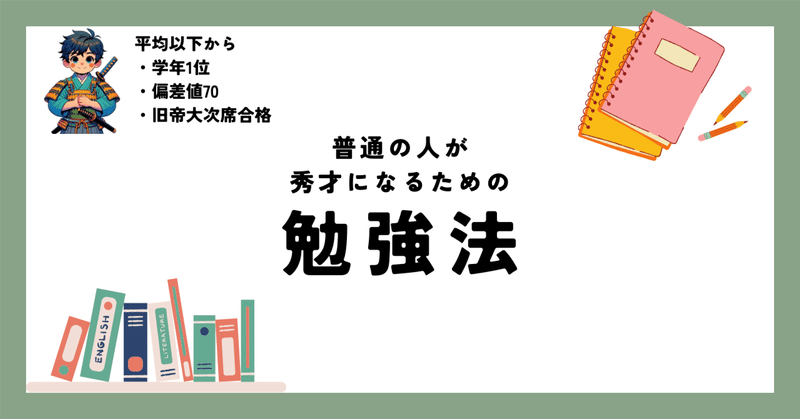
偏差値50以下から学年1位&偏差値70を取る勉強法|旧帝大次席が徹底解説
「こんなに勉強してるのになんで成績が伸びないんだろう」
これ、昔の私が悩んでいたことです。
勉強ができる人と勉強ができない人の違いはなんだと思いますか?
センス?
地頭?
環境?
残酷なことをいってしまうと、これらの要素は「勉強ができる/できない」に多少なりとも影響を与えます。
しかし、それより大きな影響を与えるものがあります。
それは「勉強法」です。
勉強法が間違っていると驚くほど成績は伸びません。
しかし、正しい方法で勉強できれば、どんな人でも成績を着実に伸ばせます。
実際、勉強法を徹底的に改善したおかげで、
平均以下だった私の学力はぐんぐん伸びていきました。
そのおかげで、定期テストでは学年1位を取れました。
しかも、2位と圧倒的な差をつけていました。(得点率で言うと総合7%くらい違ったこともある。)
また、模試でも基本的に偏差値65以上。
偏差値70を取ることだって珍しくありませんでした。
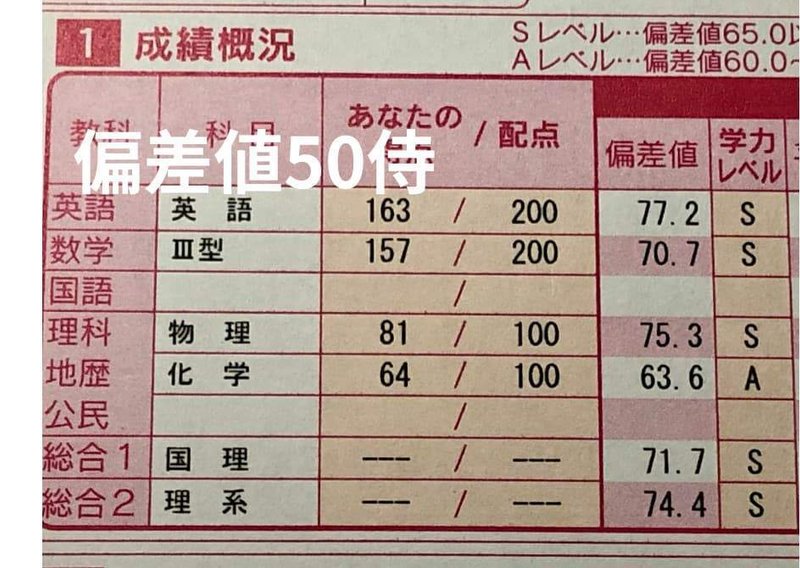
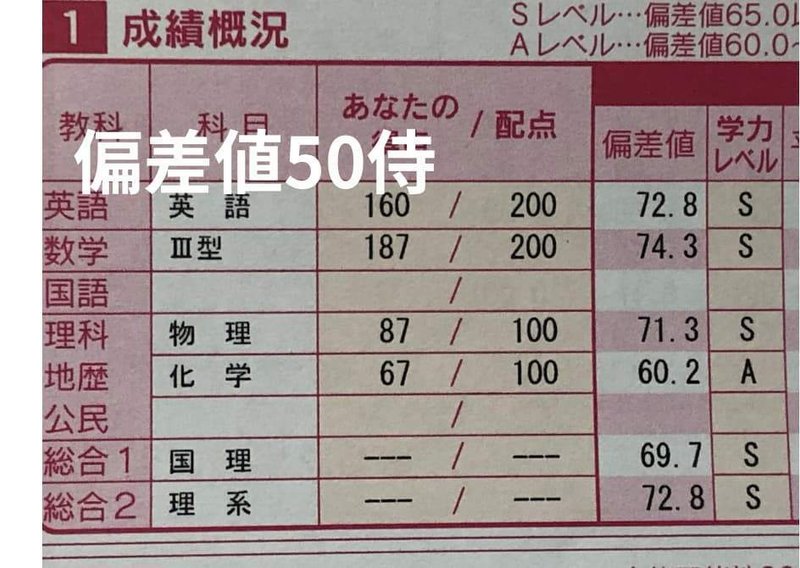

さらに、
共通テスト本番では86%
旧帝大の2次試験では87%
を取り、目標の旧帝大に次席で合格しました。
このnoteの内容を簡単に紹介!
✅勉強の基本23
国語・数学・英語・理科・社会(+副教科)。
どの科目にも通用する「勉強の基本」を徹底解説してます。
これを知っているかどうかで勉強の効率は大きく変わります。
例えば・・・
・勉強の効果=⭕️⭕️⭕️⭕️✖️🔺🔺🔺🔺
・「〇〇〇〇」と思い込むのはダメ
・集中できない時は■■■■■■■■■■■
✅国数英の具体的な勉強法
さらに、国語・数学・英語については「超具体的に」勉強法を解説してます。成績を伸ばすヒントをたくさん盛り込みました。
このnoteを購入するメリット
私が試行錯誤してたどり着いた勉強法を知ることで、
✅無駄な努力をせずに済む
✅短期間で成績がぐんぐん伸びる
✅最小の努力で最大限の結果を出せるようになる
そして、
勉強が楽しくなる!
→さらに成績が伸びる!
→もっと勉強したくなる!
→・・・
→志望校に合格する!
という未来が待っています。
このnoteはこんな方にオススメします
✅勉強で行き詰まっている方
✅正直、勉強が嫌いな方
✅成績を短期間で伸ばしたい方
✅勉強を好きになりたい方
✅まわり道をしたくない方
✅勉強でライバルと差をつけたい方
一方で、こんな方には購入をオススメできません
✅自分一人で試行錯誤しながら挑戦したい方
✅紹介している勉強法を実践しない方
✅「別に勉強なんてできなくても良いや」と思っている方
✅天才的に勉強ができる方
価格設定について
価格は2,980円とさせていただきます。
中高生には少し高く感じるかも知れません。
しかし、それだけの価値は間違いなくあると断言します。
参考書をいろいろ買い集める前に、このnoteで「正しい勉強のやり方」を学んでください。そうすれば、勉強の効率をグッと底上げでき、ライバルたちと大きく差をつけられます。
では、本編に入りましょう。
ここから先は
¥ 2,980
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
